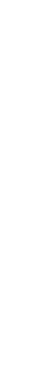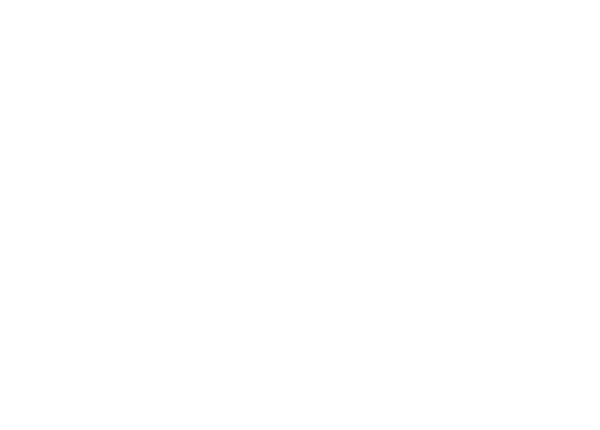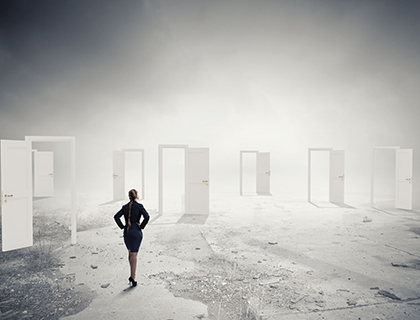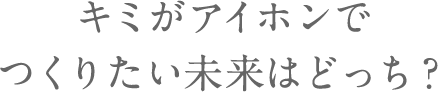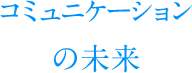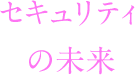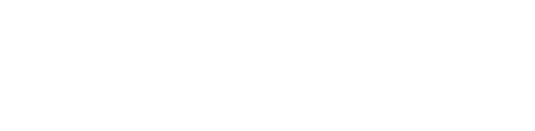- 畔柳
- 「100年後は、セキュリティの機能を強化する一方で、VR(仮想現実)なんかを活用することで、危険性を減らすこともできるんじゃないかと考えています」
- 冨田
- 「私もそう思います。自分の代わりに、たとえばロボットなんかに行動してもらえば、直接危険にさらされることがないですもんね」
- 鈴木
- 「なるほど、たしかにそうですね。一方で、国を超えてありとあらゆる人と接するようになるため、セキュリティの強化という観点で言えば、『情報』の重要性がより高まるのではとも思っています」
- 野上
- 「私も、来た人の声色から心理状態を読み取って犯罪防止につなげるような、そんなシステムを想像しました。ロボットが訪問してくる、というケースも想定しなくちゃいけないかもしれませんね」
今から約100年前、1916年と言えば、第一次世界大戦の真っ只中。皮肉にも、そのなかで培われてきたセキュリティ技術というものも、あるのかもしれません。そう思うと、この先の100年のセキュリティは、平和な世の中にするためにこそ活かしたいですね。
100年後のセキュリティ。それはもう、「こうあってほしい」という願いでいいはず。そんな理想の世の中に思いを馳せたのは、これからのアイホンを担う若手4人。100年後と言えば、自分たちこそこの世にいませんが、こどもや孫が生きている未来かもしれない。だからこそ自由に、それでいて真剣に、セキュリティの未来を考えました。

畔柳 英健
EIKEN KUROYANAGI
品質保証部 品質保証第二課
詳しくみる
危険を減らす。安全を強化する。2つの分野でセキュリティは進化する。
セキュリティと一言で言っても、考え方は2つあると思っています。ひとつは、危険そのものを遠ざけるという考え方。もうひとつは、セキュリティ機能の強化を図り、安全性を高めるという考え方です。
「危険そのものを遠ざける」というのは、具体的には、極力家から出ないで済むようにするということ。いまVR(仮想現実)の技術が盛り上がってきていますが、仮想の世界とリアルな世界が近づきつつあって、家にいながらいろんなところへ行けて、かつ行った先で「その人が来た」ということが認識される。けれど生身の人間ではないため、事故やテロに遭遇したとしても、危険にさらされることはありません。
もうひとつ、「安全性を高める」というのが、現在の延長線上の考え方。今は誰が来たか画像や声で目や耳を使って確認するしかありませんが、来た人の感情までも、声紋や虹彩、心拍数や息づかいなどをセンサーが自動的に読み取って、もしかすると五感以上の何かで危険度を測ってくれるようになるのではないでしょうか。その2方向でセキュリティが進化すれば、今よりも安心・安全を提供できるようになると思います。

鈴木 悠一郎
YUICHIRO SUZUKI
東京支店 東京電設第一営業所 東京電設第一第二グループ
詳しくみる
情報の重要性がさらに増す時代。訪れた人の考えていることまでわかるようになるのでは。
今でさえグローバルだボーダレスだと言われているのですから、100年後ともなれば、それがもうあたりまえになっているはず。しかし、育ってきた歴史や文化の違いを、お互いが100%理解しているという状況にはまだ至っていないような気がします。
そんな世界において何より重要なのは、「情報」です。ありとあらゆる人と接することになる世界ですから、会う人会わない人を賢明に判断していくことが求められると思うからです。その人がどんな人で、どんな気持ちでいるのか。事前に把握することができれば、安心・安全につながっていくのではないでしょうか。
それは、アイホンが創業以来、1対1のコミュニケーションを通じてセキュリティを考えてきた会社だからこそ、やれること。それが、「インターホン」というモノではなくなったとしても、システムや地域の仕組みをつくることで、どんな時代が来ても、「安心・安全」を提供し続ける会社でいられるのではないでしょうか。

野上 沙也佳
SAYAKA NOGAMI
名古屋支店 名古屋営業所
詳しくみる
声紋分析やトレーサビリティなど、社会のあらゆる技術がセキュリティを強くする。
それさえあれば、セキュリティは安心。そう言えるようなシステム、ロボットが登場していると思います。たとえ、言葉がわからない外国の人が来たとしても、住んでいる人になじみ深い言語で翻訳される。それも、通訳の人や機械の声ではなくて、訪問者の声色のままです。あとは、その人の声色から心理などを読み取って、その後の行動パターンなどをシミュレーションすることで、犯罪を防止するなんて機能も搭載されるといいですね。
さらに、もし危険と判断した人物がいたら、地域全体に共有してくれるとより安全性が高まりますよね。あ、100年後だったら、家に訪問してくるのは人間だけじゃなくて、ロボットもいるかもしれないですね。ロボットだと声紋分析が使えないので、瞬時にロボットのロット番号などを調べて、今日自分の家に来るべきロボットなのかどうかを判断することができる。機器そのもののセキュリティを強化するだけでなく、地域や社会とのネットワークも活用しながら、総合的に安全性を高めていくような世の中になっていると思います。

冨田 海人
KAITO TOMITA
東京支店 東日本テクニカルセンター 東日本営業技術支援第二グループ
職種を詳しくみる
安全な場所にいながら、自身のドローンロボットで行動するようになるかも。
コミュニケーションの手段が劇的に進化を遂げていると思います。話さなくても、書かなくても、脳信号レベルで意思疎通ができる。もちろん、すべてを伝えられるわけではないため、セキュリティは変わらず必要な世の中になっているでしょう。
ただ、家に来た人の情報を地域のビッグデータなどから照合することができて、もし前科のある人や不審な行動をとっている人が来たら、直接警察へ通報することができる。その操作さえもロボットにプログラミングしておけば、自動的にフィルタをかけて、本当に会うべき人にだけ会えるようになる。そんなサービスになっていくのではと思います。
また、危険なところに出かけるときも自分が出かけるのではなく、体を完全に安全な場所に置きながら、自分のドローンのようなロボットをつかって行動すれば、危険にさらされることはありませんよね。カメラやマイク、触覚センサーなどを通じて、家にいながらリアルな感覚を得ることができる。人とロボットが近づいていくことが、セキュリティの究極かもしれませんね。