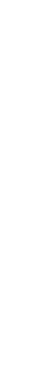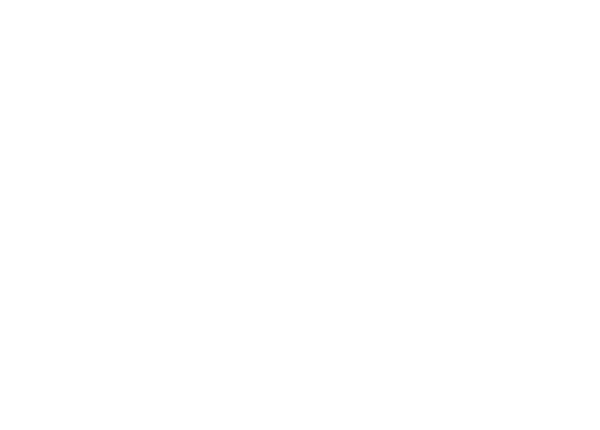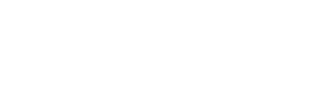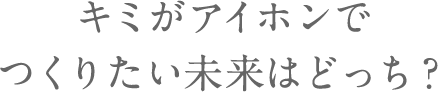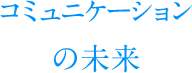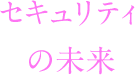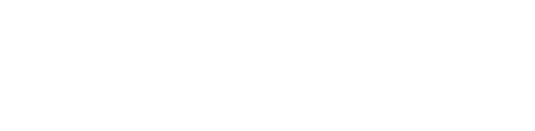- 三浦
- 「50年後ともなれば、現代では想像がつかないほど安心できるものが生まれていそうですよね。ただ、万能ではないはずです。アイホンが手がけるべきは、そこからこぼれ落ちたような、けれども欠かすことのできない分野なのではと思っています」
- 峰田
- 「そうですね。アイホンは、世の中の身近で必要とされる部分に焦点を当てて、安心・安全を届けてきた。私はインターホンという枠を超えて、より社会問題に取り組むことで安心・安全に貢献しているんじゃないかと想像します」
- 伏屋
- 「私も、ハードとしてのインターホンからより発展して、ひとつのデバイスに集約されていると思います。アイホンはその操作性やメンテナンス、利便性の分野で価値を提供しているかもしれませんね」
- 三浦
- 「いずれにしても、他社がやらないことで、かつ他社が実現し得ない品質を追求するのが、『アイホンの良さ』。そこを守ることが、他社との差別化になると思います」
50年前、ロボットが受付をし、接客をしてくれる店が本当に登場するなんて、どれだけの人が想像したでしょうか。技術の進歩は、加速度的に速くなっています。過去の50年とは比べ物にならないほど、これからの50年はさらに変化をしていくでしょう。そんな50年後のセキュリティを考えたのは、現在のアイホンの中核を担う30~40代の面々。セキュリティは、そしてアイホンはどんな価値を創造しているのか。それを考えるとき、図らずも創業から現在までの歴史を振り返ることで、見えてくることがありました。

三浦 勇吾
YUUGO MIURA
商品企画課 マーケティング企画課 課長
詳しくみる
50年後も、派手じゃないところで確実に人の役に立つ何かを一生懸命提供しているはず。
50年後、アイホンが何をやっているかを考える前にまず、何を大切しているかを確かめておきたいと思います。私は、アイホンのコアコンピタンスの一つは、「事業領域の妙」だと思っています。「インターホン」という、目立たないところに目をつけたこと。そしてその品質を追求してきたこと。それが大きな成功要因ではないかと思っています。
例えばアイホンの集合マンション用インターホンは消防検定品の認定を受けていますが、様々なチェック項目によって高い品質が求められる商材です。いわゆる“作りやすく売りやすい”商材ではありません。そのハードルの高さがそのまま参入障壁になっているのですが、言い換えれば、他社があまりやりたがらないことをやっているということです。それこそが強みであると思います。
50年後も、きっといろんな便利なものが登場しているはずですが、完全に万能なものではないはずです。その「抜け」や「すき間」の部分を、アイホンがフォローしていくことで価値を生み出していけるのではないかと思っています。それは、扱う商材が“モノ”から“コト”に切り替わっていたとしても、販売流通の構造が変化していたとしても、本質は変わりません。50年先も変わらず、先人たちの思いを引き継ぎながら、守っていく。それが、他社との差別化となり競争優位に繋がっていくのではないかと思います。
現在、国内においては超超高齢化社会を見据えて、アイホンだけでなく他社とのアライアンスによって様々なシステム試験を進めています。海外においては、各国の文化や慣習を踏まえた商品企画・販売ができる体制を目指しています。そういったことがしっかり発展し、派手ではなくともさりげなく社会の課題を解決するような会社であってほしいですね。

峰田 哲朗
TETSUROU MINEDA
営業推進部 医療・介護市場担当 担当課長
詳しくみる
高齢化、環境問題、エネルギー、食糧… 世界の諸問題に取り組むようになるのでは。
アイホンは、身近で、かつ社会から必要とされている事柄に焦点を当て、安心・安全を届けてきました。だからきっと、50年後もそうした社会問題と自社の技術や強みを組み合わせて価値提供しているように思います。
たとえば、超超高齢化。1000万人ほどいると言われる「団塊の世代」が後期高齢者(75歳以上)になるのが、2025年。50年後はそのずっと先のことですから、いま国が推し進めている「地域包括ケアシステム」はその頃には定着しているんじゃないでしょうか。要は、家で最期を迎えるようになるということ。自宅にいながら病院や介護施設とネットワークでつながっていて、解読されたゲノムを使った遺伝子レベルでの診察を受けることができる。そんなシステムの構築に携わっているように思います。
他にも環境やエネルギー、食糧などが世界規模で問題になってくるはず。だからもしかしたら、安心・安全という枠組みで、これらに対応するシステムを構築しているかもしれない。もちろん、海外において新興国ではまだネットワークの恩恵を受けられない地域もあるかと思います。そこではまだインターホンとしての機能が重要視されているかもしれませんね。いずれにしても、世界がボーダレス化しさまざまな人と人、人とモノが接する機会が増えれば増えるほど、セキュリティのニーズは高まっていくと同時に新たな価値が生まれるように思います。

伏屋 友樹雄
YUKIO FUSEYA
商品開発部 商品開発チーム 主事
詳しくみる
高度なセキュリティを自動化していく事は近い将来、技術的に可能になっていくと思います。
50年後にはもう、目的ごとのデバイスではなく、すべてを集約したものがあるはずです。制御するハードはそれ1台で、周辺機器やソフトを売っていく。特にソフトの比重が大きくなり、ソフトで柔軟に対応しているように思います。
時代が変わっても大切なのはコミュニケーションとセキュリティ。アルツハイマーを患った方がふらっと出かけてしまったのを追跡することができたり、通学路の防犯として機能していたり。いわゆるロボットにその役割を担わせるのは、近い将来可能になるのではないでしょうか。ただ、そうなったときにメンテナンスはどうするのか、コストは、動力はなどさまざまな問題はあります。また、セキュリティをまかせたなら、いついかなる状況であっても画像や動画を鮮明に残すことが必要になってきますが、反対にプライベートを守る必要もあります。セキュリティ機能の高さと利便性をいかに両立させていくかがカギになると思います。